介護離職ゼロの社会へ──日本顧問介護士協会・石間洋美理事長が語る「親の介護と仕事の両立」 最終更新日:2025/11/19

「親の介護で仕事を辞めない社会をつくりたい」──そんな想いから活動を続ける、一般社団法人日本顧問介護士協会の石間洋美理事長。
本インタビューでは、介護離職が生まれる背景や、親の介護にかかる費用の実情、そして企業や地域が果たすべき役割についてお話を伺いました。
介護と仕事の両立に悩む方、介護離職防止に取り組む企業関係者にとって必読の内容です。
本インタビューでは、介護離職が生まれる背景や、親の介護にかかる費用の実情、そして企業や地域が果たすべき役割についてお話を伺いました。
介護と仕事の両立に悩む方、介護離職防止に取り組む企業関係者にとって必読の内容です。
「ありがとう」から始まった物語──親の介護を支えたい想いと転機
— 石間さんは20年以上、介護の分野でキャリアを積んでこられたとのことですが、そもそも介護の道に進まれたきっかけは何だったのでしょうか?
もともとは保育士になりたかったんです。高校も保育コースがある学校を選びました。ですが、高校でのボランティア活動が大きな転機になりました。
ボランティアで介護施設を訪れたとき、ご高齢の方々の身体が病気や加齢で変化している姿を目の当たりにして、大きな衝撃を受けました。それと同時に、私のような学生が施設に行っただけで、あるおばあちゃんが「来てくれてありがとう」と涙を流して喜んでくださったんです。その時、「自分がいるだけで、こんなにも感謝されることがあるんだ」と、自分の存在価値を強く感じました。この経験から、人の役に立てるこの世界で専門性を高めたいと思うようになり、介護福祉の専門学校へ進むことを決めました。

— 専門学校での2年間はいかがでしたか?
実習などを通じて、ボランティアで見ていた世界とは違う、介護現場の厳しさや過酷さを学びました。知識や技術を学んでも、現場ではなかなか通用しないことも多く、理想と現実のギャップを感じながら試行錯誤する毎日でしたね。
— 卒業後は、介護老人保健施設(老健)で6年間、現場の介護福祉士として勤務されたそうですね。そこではどのような経験をされましたか?
老健は、亡くなるまで過ごす「看取り」の場と、リハビリを経て自宅へ戻るための「回復」の場という、両方の側面を持っています。そのため、回復して元気に退所される方の喜びにも立ち会いましたし、多くの方の最期にも向き合ってきました。その中で「本当にこの方の人生にとって、ここで最期を迎えることが最善だったのだろうか」と、深く死生観について考えさせられる日々でした。

— 現場で最も大きな学びとなったことは何でしょうか?
人間の身体の繊細さと、生きる気力の大切さです。例えば、ご高齢の方は高熱を出して3日間寝たきりになるだけで、それまで歩けていた方が歩けなくなってしまうことがあります。一方で、ほとんど寝たきりだった方が、懸命なリハビリと周囲の関わりによって、再び自分の足で歩けるようになったり、スプーンでご飯を食べられるようになったりするんです。そういった「生きる力」が湧き上がってくる瞬間に何度も立ち会い、人の可能性や関わり方の大切さを学びました。「もう年だから」と諦めないこと、そして周囲が諦めずに支え続けることの重要性を痛感しましたね。
親の介護で退職はもう古い?介護離職を防ぐためにできること
— 現場経験を経て、マネジメント職に転身されています。どのようなお仕事だったのですか?
介護施設の生活相談員や施設長として働きました。ご家族様への施設の案内や入退所の手続き、料金説明、そして介護保険制度に基づく行政への対応など、業務は多岐にわたりました。ここで、介護現場を外から支える仕組みや、介護にいくらかかるといった経営的な視点を学ぶことができました。
— その後、2020年に一般社団法人日本顧問介護士協会を設立されました。協会設立の背景には、どのような想いがあったのでしょうか?
介護保険制度が始まって以来、介護報酬だけで施設を運営していくことが非常に厳しくなっている現実がありました。一方で、企業では従業員の介護離職という深刻な問題もあったんです。この二つの課題を結びつけ、介護の専門知識を活かして企業の福利厚生として「両立支援」を行うことで、保険外の新たな収益モデルを確立できるのではないかと考えたのが始まりです。家族の介護で退職せざるを得ない状況は、企業にとって大きな損失ですし、働く人にとってもキャリアが途絶えてしまう不幸なことだと感じました。その不幸をなくしたいという想いで協会を立ち上げたんです。

— 協会の大きな目標を教えてください。
究極の目標は「介護離職ゼロの社会」を実現することです。しかし、それは1つの会社、1つの団体だけで成し遂げられるものではありません。企業同士が連携し、さらには地域社会全体で介護者を支える仕組みづくりが必要です。私たちは、その連携のハブとなる存在でありたいと考えています。
— 協会が掲げる「顧問介護士」とは、どのような役割を担うのでしょうか?
企業の従業員様が仕事と家族の介護を両立できるよう、専門家の立場からサポートする役割です。協会が会社と契約することで、その会社の従業員様は、介護に関するあらゆる相談に個別で、かつ無料で何度でも対応してもらえるようになります。親の介護は非常にプライベートな問題であり、社内の人には相談しづらいという方も多いため、私どものような第三者の専門家が相談窓口となることで、安心して悩みを打ち明けていただけます。
— 協会を設立されたのはコロナ禍の真っただ中だったそうですが、ご苦労もあったのではないでしょうか。
はい、設立当初は本当に大変でした。2020年に、私を含めた3名でスタートしたのですが、当初は法人向けのサービスとして、企業へ直接訪問してご提案する計画でした。実際に大手企業様との契約も決まっていたのですが、コロナ禍でそれが一切できなくなってしまったのです。計画は白紙になり、一時は活動が完全にストップしてしまいました。
— その苦しい状況をどのように乗り越えられたのですか?
対面での活動ができないなら、オンラインでできることを模索しました。その一つが、LINEを活用した個人向けの介護相談サービスです。これが後の「わたしの介護相談」につながっていきます。また、コロナ禍を経て社会の働き方が大きく変わったことで、リモートでの相談やセミナーの需要が高まり、結果的に私たちの活動の幅を広げることにつながりました。ピンチがチャンスになった形ですね。
企業の介護離職問題に終止符を──法人向けサポートで両立を支援
— 現在、法人向けにはどのようなサービスを展開されていますか?
メインは先ほどお話しした「顧問介護士サービス」です。現在120社ほどの企業様にご導入いただいています。この他に、旭化成ホームズのオーナー様向け会員サイトでの「オンライン相談窓口」の運営、介護に関する「セミナー・勉強会」の開催、「介護支援推進企業 認定マーク」の付与、そして「介護まるごとアドバイザー認定講座」の運営など、介護離職を防ぐためのサービスを多角的に展開しています。

— 旭化成ホームズ社のオンライン相談窓口とは、どのようなものでしょうか?
旭化成ホームズ様がご自宅を建てられたオーナー様向けに提供している「HEBELIAN NET.」という会員サイトの中で、私たちが介護相談の窓口を担当させていただいています。オーナー様ご自身の介護の悩みはもちろん、親の介護に関するご相談に、専門家として一件一件丁寧にお答えするサービスです。このようなオンライン相談のほか、法人向けの「顧問介護士サービス」を含め、これまで20,000件以上やりとりしてきましたが、クレームは一件もありません。顔が見えないオンラインでのやりとりだからこそ、機械的なものではなく、真心を込めた対応を心がけています。
— セミナーや勉強会の需要も増えているそうですね。
はい。2022年4月の育児・介護休業法の改正により、企業は40歳以上の従業員に対して、介護休業制度などを周知することが義務付けられました。その周知の一環として、親の介護に費用はいくらかかる?といった金銭的な不安から、具体的な制度の活用法まで、介護に関するセミナーや勉強会を開催したいという企業様からのご依頼が非常に増えています。現在は月に20本ほど実施しており、介護離職を防ぐための重要な第一歩としてご活用いただいています。

— 「介護支援推進企業 認定マーク」という制度も興味深いです。これはどのようなものでしょうか?
仕事と親の介護の両立支援、つまり介護離職防止に積極的に取り組んでいる企業様を、私たちの協会が審査し、認定する制度です。審査項目はいくつかありますが、従業員が働きやすい環境を整備していればクリアできる内容になっています。この認定マークを取得することで、企業のイメージアップや社会的信頼性の向上につながり、「採用効率が上がった」というお声を多くいただいています。
— 「介護まるごとアドバイザー認定講座」についても教えてください。
これは、介護に関する本当に基礎的な知識を3時間半で学べる講座です。コンセプトは「身近な介護相談員」です。介護現場で働くための専門的なものではなく、例えば企業の人事担当者の方が従業員からの相談に対応するための知識を得たり、保険の募集人の方がお客様に介護保険商品を提案する際の基礎知識として学んだりと、法人研修としてもご活用いただいています。もちろん、今まさに親の介護に直面しているご家族様にも役立つ内容です。
親の介護にかかる費用はいくら?現実的な金額と支援制度を解説
— 法人向けだけでなく、個人向けのサービスも提供されているのですね。
はい。「わたしの介護相談」というサービスです。これは、年間13,200円(税込)の会費で、1年間何度でもLINEで介護相談ができるというものです。行政の窓口ではなかなか得られない、もっと踏み込んだ情報や具体的なアドバイスを提供することで、ご家族が一人で抱え込む状況を防ぐことを目的としています。

— 具体的にはどのような相談が多いのでしょうか?
本当に様々です。「親がこういう状態なのだけど、もう介護保険を申請するレベルなのだろうか?」といった初期段階のご相談から、「親の介護にかかる費用は、一体いくらなのか見当もつかない」「病院からもうすぐ退院と言われたが、このまま自宅で生活できるのか、施設に入れた方がいいのか判断できない」といった切実な悩みまで、多岐にわたります。
— サービスの特色は何でしょうか?
私達が最も大切にしているのは、単なる情報提供に留まらない、血の通った「愛とぬくもり」のサポートです。特に施設選びのご相談では、ご希望の地域や予算、ご本人の状態などを詳しくお伺いし、私たちが実際に候補となる施設へ電話で問い合わせ、空き状況や受け入れ体制、電話口の雰囲気などを確認した上で情報提供します。ネットの情報だけでは決して分からないところまでしっかりと感じ取っていただきたい、そんな想いで一つひとつのご相談に対応しています。
— そこまで調べてくださるのですね。
はい。ただリストを渡されて「自分で選んでください」では、ご家族様は何を基準に選んでいいか分かりません。私たちは、電話対応の印象といった主観的な情報も含めてフィードバックすることで、ご家族様がより安心して施設を選べるようサポートしています。私たちの強みは、全国どこでも対応できることです。ご相談内容によっては、電話で調査を行い、詳細な情報をお返ししています。
— LINE以外での相談も可能ですか?
はい、LINEでのやりとりは回数無制限ですが、オプションとしてZoomでのご相談も承っています。こちらは40分5,500円(税込)で、より深くお話を伺うことが可能です。申し込みは、私たちの協会のウェブサイトから簡単に行えます。
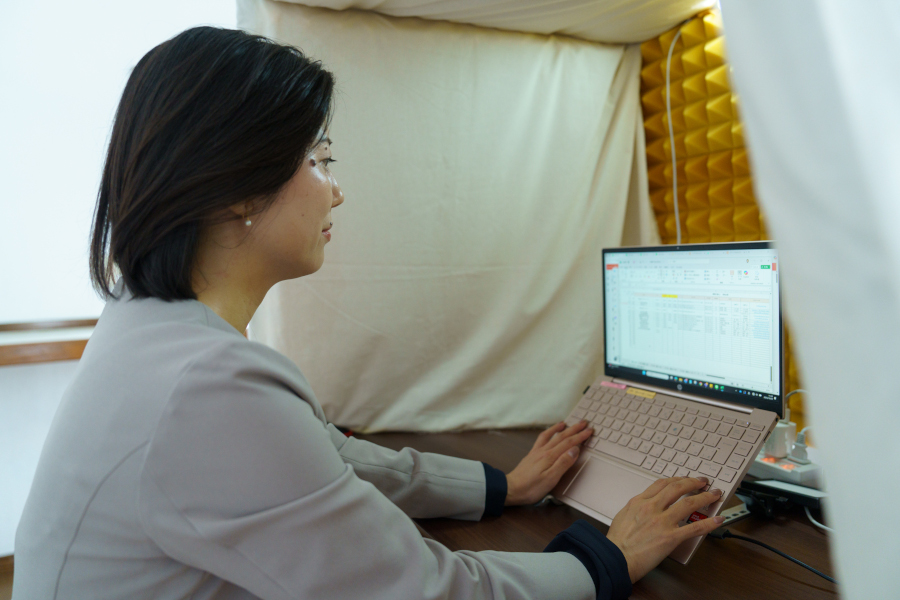
— このサービスを利用されたお客様から、たくさんの感謝の声が寄せられているそうですね。
「おかげで無事に施設に入居できました」といった感謝の言葉をいただくことはもちろんあります。また、仕事を辞めることを検討されていた方が、私たちの提供した情報を基にご自身で判断し、結果的に介護離職をせずに済んだケースもあります。選択肢を知らないだけで追い詰められてしまう方は本当に多いので、私たちが介在することで少しでもお力になれたらと思っています。
介護離職ゼロの未来へ──企業と地域が支える新しい共助のかたち
— 石間さんが今、介護において最も大きな課題だと感じていることは何ですか?
やはり、介護の悩みを「一人で抱え込みやすい」という社会の構造です。介護はプライベートな問題だからと、職場でも誰にも言えずに苦しんでいる方がたくさんいます。親の介護と退職を天秤にかけざるを得ない状況が、介護離職につながる大きな原因だと感じています。また、上司や同僚も、部下が介護で大変そうだと分かっていても、どう声をかけ、どうサポートすればいいか分からず、結果的に見て見ぬふりをしてしまう。この双方のコミュニケーション不足が問題です。
— その課題を解決するために、今後どのように取り組んでいきたいですか?
私たちのような第三者の専門家が、企業と従業員の間に入り、双方を適切に導いていくことが不可欠だと考えています。そして将来的には、1つの企業だけで抱えるのではなく、複数の企業や地域全体が連携して介護者を支える仕組みを作っていくべきだと思っています。例えば、いくつかの企業が協力して、「託児所」のような地域企業型の「宅老所」みたいなものを作って、そこに専門家を配置して親御さんを預かってもらえるような環境があれば、従業員は安心して仕事に集中できますよね。

— 企業や社会の連携が鍵になるのですね。
はい。1社だけでは難しいことも、複数の企業が協力すれば可能になります。私たちはそのハブとなり、企業同士、あるいは企業と地域社会をつなぐ役割を担っていきたいと考えています。介護離職ゼロは、決して一つの会社だけで実現できるものではありません。社会全体で支え合うという意識を醸成していくことが、私たちの使命です。
— 最後に、今介護に悩んでいる方や、これから介護に直面するかもしれない皆さんへメッセージをお願いします。
介護は、誰にでも突然訪れる可能性があります。その時、親の介護で退職を考える前に、どうか一人で抱え込まないでください。介護にいくらかかるかという費用面の不安も、専門家が一緒に考えることで道筋が見えてきます。今は、行政の窓口だけでなく、私たちのような民間の専門家もいます。相談する相手をきちんと見極め、信頼できる専門家を頼ることが、あなた自身の人生とキャリアを守るための第一歩です。私たちは、介護をする人が笑顔でいられる社会を目指しています。いつでも気軽に声をかけていただければ嬉しいです。

一般社団法人日本顧問介護士協会

わたしの介護相談:親の介護や介護離職の悩みを専門家に相談しよう
サービス対象者:親の介護があるため、仕事に支障が出てしまう、、、どうすればいいのか?という方!
解決する課題:こんな悩みを解決します!
・遠方で両親の介護が難しい。どの施設を選んでいいのかわからない。
・介護について家庭内で協力が得られず一人で抱えていて疲弊している。
・誰に相談して良いのかわからない。
・在宅介護が不安。
・介護申請や手続きの仕方がわからない。
・介護施設に入居するとき、今住んでる家をどうしたらいいかわからない。
・遠方で両親の介護が難しい。どの施設を選んでいいのかわからない。
・介護について家庭内で協力が得られず一人で抱えていて疲弊している。
・誰に相談して良いのかわからない。
・在宅介護が不安。
・介護申請や手続きの仕方がわからない。
・介護施設に入居するとき、今住んでる家をどうしたらいいかわからない。
サービス内容:「LINE」友達登録で、介護のプロ「わたしの介護相談」がご対応させていただきます。
利用方法:面会不要、チャット相談で完結します。
利用料金:年会費13,200円(税込)
オプション:zoom相談40分5,500円(税込)
お申込み方法:以下からお申込みください。お支払いはクレジット決済となります。
お問い合わせ
〒424-0806
静岡県静岡市清水区辻三丁目1番2号
TEL:054-625-5212
MAIL:https://www.komonkaigo.jp/contact/
WEB:https://www.komonkaigo.jp/
静岡県静岡市清水区辻三丁目1番2号
TEL:054-625-5212
MAIL:https://www.komonkaigo.jp/contact/
WEB:https://www.komonkaigo.jp/
石間洋美 理事長のプロフィール

経歴:
2003年 学校法人中村学園 静岡福祉医療専門学校 卒業
2003年 医療法人社団駿甲会 介護老人保健施設(介護職員)
2009年 医療法人社団R&O 介護老人保健施設(介護事務員)
2012年 株式会社アース(コンプライアンス室長、生活相談員、介護施設長)
2018年 株式会社フォーエバー(統括マネージャー)
2020年 一般社団法人日本顧問介護士協会設立
現在に至る
2003年 学校法人中村学園 静岡福祉医療専門学校 卒業
2003年 医療法人社団駿甲会 介護老人保健施設(介護職員)
2009年 医療法人社団R&O 介護老人保健施設(介護事務員)
2012年 株式会社アース(コンプライアンス室長、生活相談員、介護施設長)
2018年 株式会社フォーエバー(統括マネージャー)
2020年 一般社団法人日本顧問介護士協会設立
現在に至る
親の介護・介護離職に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 両親が二人で暮らしているが、最近買い物などが大変そうです。何かサポートしてくれるサービスはありますか?
A. 65歳以上であれば、介護申請が可能となります。介護サービスを利用することができれば、介護保険内で買い物代行などのサービスを受けることができます。
Q2. 親の認知症が進行し、昼間に寝てしまい、夜間活動的になっています。日中は仕事をしているので、夜間に目が離せなくなると睡眠不足になっていまいます。家で出来る仕事に切り替えるべきなのか悩んでいますが、どうすれば良いのでしょうか。
A. まずは、主治医に相談しアドバイスを受けてください。並行して介護保険サービスを効果的に利用することも考えてみては。「小規模多機能型居宅介護」等の介護保険サービスの利用が良いかもしれません。
Q3. 遠方に暮らす親に介護が必要な状態となり、介護サービスを利用しながら生活しています。月に一度は通院があるため帰省して付き添っていますが、毎月の遠距離移動も大変です。帰省のたびに「いつ実家に戻ってくるのか?」と聞かれるため、今の仕事を辞めて戻ろうか悩んでいます。どうすれば良いのでしょうか。
A. 自治体によっては、高齢者の一人暮らしを支えるサービスを提供している場合もあります。地域包括支援センターに相談して、地域で見守ってくれる体制に参加してみては。また、適切な介護サービスの選定し、警備会社の見守りサービスを導入して遠距離でもサポートできる環境を作ってみてはいかがでしょうか。
Q4. 父が脳梗塞で入院しています。退院後、本人は自宅に戻れると思っているが、今までのように生活できるのかわからない。どうしたらいいのでしょうか?
A. 自宅での生活か、介護施設での生活か、まずは検討してみてください。その際、住環境や家族の介護力、介護のかけられる費用等を家族で話し合うことが大切です。どれくらいの介護量になるか想像がつかない場合には専門家へ相談し、その上で後悔のない選択をするようにしてください。
Q5. 母がデイサービスを利用し始めたが、嫌がって休んでしまいます。このまま介護サービスを利用しないと自分が仕事を辞めて世話をするしかないのですが、どうすれば良いのでしょうか。
A. デイサービスの種類はいくつもあるので、利用しやすい事業所を選ぶことが大切です。いくつかのデイサービスをお試し利用しながら選定してみてください。また、ケアマネジャーと相談しながら、介護サービスを組み合わせていくことも重要です。

関連リンク:









